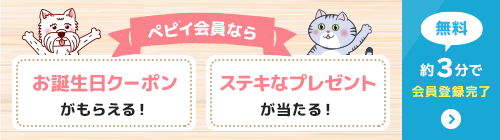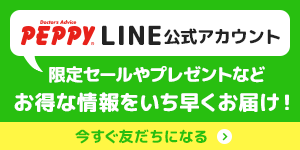VOL.9 群馬県動物愛護センター 編
めざせ!満点飼い主!
「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」で、より良い飼い主さんの
育成とサポートを行う施設
北関東自動車道前橋南ICから車で約10分の場所に位置する群馬県動物愛護センター。
同センターは前橋市と高崎市を除く県内すべての動物愛護業務を担っています。
動物の収容能力は犬50頭、猫20匹と小規模ですが、きれいに清掃された館内は動物がいることを忘れるほど清潔。
犬猫収容室ほか、観察犬室、治療室、譲渡動物飼育室に屋外ドッグランと必要な施設はすべて整っています。

同センターが目指すは「満点飼い主さんの育成」
「すべての飼い主さんが満点飼い主さんなら、ここに来る犬猫は、いなくなるはず!」。
そんな願いを込めて、令和2年末から動き出したのが、「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」(※1)です。!
「きめ細やかなアドバイスができて、飼い主さんが正しい犬猫の飼い方ができるよう、サポートするネットワークを整えたい」
同センターが「満点飼い主さん育成」のために取り組んでいる様々な活動をご紹介します!

目次
・「群馬県動物愛護センター」のここがポイント
官民一体の協力体制で、飼い主さんを手厚くサポート
・「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」に登録しているドッグトレーナーさんに聞きました!
「群馬県動物愛護センター」のここがポイント
官民一体の協力体制で、飼い主さんを手厚くサポート
同じ北関東に位置しながら他の二県(茨城県・栃木県)と異なる現状を持つ、群馬県動物愛護センター。
茨城県、栃木県ではまだまだ野犬の収容率が高い中、高崎市・前橋市を除く群馬県動物愛護センターでの野犬収容率はゼロ。
ここに来る犬のほとんどが迷い犬で、うち約6割がもとの飼い主さんに返還されています。
多くの理由が、北関東で頻繁に起こる強烈な落雷に驚いて犬がパニックになり、リードを引きちぎった、係留していたリードが劣化して逸走した、など、飼い主さんの管理に課題が多いと言います。
そのため、ニュースレター等(※2)を利用して所有者明示の大切さや迷子札、マイクロチップ装着の重要性を広く啓発していますが、収容犬で所有者がわかるマイクロチップ等の装着は一割以下。これら収容犬の問題は、飼い主さんの飼い方次第で簡単に解決します。
そこで始まったのが、犬や猫の飼い主さんを官民協働でサポートをする「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」です。
この制度の目的は大きく分けて二つ。
ひとつめは「犬猫を適正飼養し、終生飼育できる飼い主さんを増やすこと」。
そのためには、飼い主さん自身が、飼育している動物について広く知り、また学ぶ体制を整えておくことが大切です。
そしてふたつめが「譲渡事業を知ってもらうこと」
知識があり、犬猫を大切に可愛がっている飼い主さんでも、災害や家庭環境の変化など様々な事情から飼っている犬や猫を手放さざるを得ない状況になる場合があります。
その時の「受け皿」に「新しい飼い主さんに譲り渡す」という選択を飼い主さんに広く知ってもらうことは「命を捨てさせない」大切な取り組みとなります。
しかしながら、動物愛護センターだけで個々の飼い主さんをサポートするのは現実的に不可能。
そこで、日ごろ飼い主さんの身近にいる動物病院、ペットショップ、トリミングサロン、ペットホテル、ドッグスクールなどの第一種動物取扱業者さん、保管業者さん、訓練業者さんなどに呼びかけ、飼い主さんのサポートに協力してもらえるような制度を立ち上げました。

事業者さんに協力していただく主な内容は「飼い主さんへの正しい犬猫の飼い方指導」「飼い方指導のチラシなどの配布」などで、登録済の事業所には「パートナー証」と制度の登録を示すステッカー(※3)を、動物病院内、店内、施設内などに提示してもらいます。
このパートナーシップ制度の登録には登録基準(※4)があり、すべての基準を満たしている42事業所がすでに登録を終え、現在、パートナーとして積極的に活動しています。
「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」に登録しているドッグトレーナーさんに聞きました!
群馬県高崎市の動物愛護推進員を務める諸星清美さん。
諸星さんは、プロのドッグトレーナーとして、家庭犬のトレーニングを行う傍ら、「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」に登録。犬の問題行動で悩む飼い主さんたちのサポートをしています。
飼い主さんの悩みに寄り添うだけではなく、犬の長所を見つけ、その長所を伸ばせるよう飼い主さんにアドバイスするのが、諸星さんのサポートのモットーです。
また諸星さんは動物愛護センターからの要請を受けて、動物愛護センターのボランティアさんの育成もサポート。
必要に応じてボランティアさんのための「犬のハンドリング実技講習」(※5)を行っています。
動物愛護センターでボランティアをしたいという人は、犬や猫が好き!という理由から。中には好きだけど家庭の事情で飼えないからボランティアを通じて犬や猫と触れ合いたいという人もいます。

▲動物愛護推進員を務める
諸星清美さん
しかし、ボランティアは「好き」という理由だけでは務まらないと諸星さん。
「ここにいる犬たちが、なぜここに収容されているのか、まずは正しく知ることが大切です。ここに来る犬たちは、様々な事情で飼い主さんと暮らすことができなかった子たちで、センターは社会復帰の入り口。様々な事情をかかえた犬たちの個々にあったお世話をしなくては、社会復帰が難しくなります」
世話の仕方によっては一歩前進どころか、一歩も二歩も後退することになりかねません。
センターでのボランティア活動は、「犬とはこういうもの」という先入観を持たず、それぞれの犬を客観的に見て臨機応変に対応できることが重要と諸星さんは常日頃から伝えています。
「ボランティアは飼い主ではなく、あくまでも一時的なお世話係。ここから別の飼い主さんのところへ送り出すんだということを心に留めて、お世話をしてほしい」
ボランティアさんは、犬たちにとって社会復帰の場で接する「最初の人間」です。
「人間の代表」として、「人っていいもんだなあ」と犬に信頼してもらうことがボランティアをする上での大前提となるのです。
「階段をポンポンと駆け上がる犬もいれば、一段、また一段ゆっくり上る子もいる。一段も上れない子もいる。その子が持っている長所を最大限に伸ばし、新しい飼い主さんにお渡しする時にはきちんと短所も伝え、納得して受け入れてもらうことが、その子の本当の社会復帰に繋がります」
犬と飼い主は一対。飼い主さんがその子の長所も短所もひっくるめて、愛情を注げるかどうかが、今後のその犬の幸せを大きく左右するのです。
「人と犬とは全く違う生き物です。まずは犬と言う生き物に対して正しい知識を十分に持つことからボランティアを始めてください」
そう語る諸星さんの「犬のハンドリング実技講習」は「犬と人とを繋ぐリードが緩み、4本足すべてが地面に着いた状態」を目指すことだと言います。
ドッグ・トレーナーさんの中には「オフ・リード(リードなし)」を目指している方が少なからずいますが、それは文字通りの「リードなし」という意味ではなく、リードで飼い主さんが強制的にコントロールしなくても、犬自身がセルフコントロールできるという意味。
その状態は諸星さんが言うように、犬自身が落ち着いている証拠でもあり、飼い主さんも安心して楽しくお散歩に行けるということなのです。
「セルフコントロールを教えることはとても大切。興奮状態では何も学習できないし、人の言うことなど耳に入りません。落ち着いて散歩する時間は、運動以上に、犬にとって飼い主との関係づくりや気分転換になる貴重な時間。リードを緩めて歩けた時には、犬をめいっぱいほめてあげてください」
動物愛護センターに来る犬たちの幸せは、人間とのリードを通した信頼関係から始まります。

▲諸星さんが目標としている「リードが緩み、4本足が地面についた状態」
「群馬県動物愛護センター」のボランティアさんに聞きました!
ドッグトレーナー諸星さんの指導を受けて、五年ほど前からセンターでボランティアを続けている群馬県動物愛護推進員の斎藤恵美子さん。
斎藤さんが担うのは、収容犬の散歩、シャンプー、譲渡会でのお手伝い等。
「仕事をしているので、私がセンターで犬のお世話をするのは月に二日ほど。犬の散歩はもちろん、犬のシャンプーも行いますが、ここにはプロのトリマーボランティアさんも来てくれるので、爪切り、耳掃除などはプロの方にお任せして、自分にできることをできる範囲でやっています」
忙しい仕事の合間をぬって斎藤さんがボランティア活動をしているのには明確な理由があります。
「私も犬が好きで犬を飼っています。今まで飼った子たちは訓練犬、繁殖犬、競技犬をリタイヤしたいわばキャリアチェンジ組。第二の犬生を踏み出した子たちです。そういった意味ではセンターの犬たちも同じ。社会復帰して第二の犬生を歩みだす最初のお手伝いをしたい。そんな気持ちでボランティアを続けています」
収容犬の譲渡会では、犬と飼い主さんとのマッチングが一番大切。そんな時、ここでのボランティア活動がとても役に立ちます。
「普段、犬と接しているので、その子の長所、短所、気を付けなくてはならないことなどを説明することが、犬と飼い主希望者さんとの幸せの第一歩に繋がります。ベストマッチする飼い主さんのところへ送り出すことがボランティアの一番の役目。できればもっと、もっと、頻繁にここに来て、それぞれの犬の状態を知り、譲渡会でのマッチングに役立てたいと思っています。」
センターのボランティアさんは、犬や猫たちの失敗なき社会復帰を橋渡しする大切な役割を担っています。
その先にはどのボランティアさんの中にも「今度こそ必ず幸せになってほしい」という願いが込められていると斎藤さんは語ってくれました。

▲ボランティアさんと散歩中のムックくん
「群馬県動物愛護センター」の繋ぎたい小さな命
群馬県動物愛護センターでは、「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」のような良い飼い主さんを増やす啓発活動と並行して、譲渡活動にも力を入れています。
センターに収容された犬猫たちは、保護期間の一週間を過ぎた後、譲渡適性観察(※6)を経て譲渡へ。
観察のチェック項目は5つあり、一項目3点から0点の点数制で合計10点以上なら「譲渡適」。
ただし、10点以下でもさらなる観察結果で可能と判断できれば「譲渡」とし、新しい飼い主さんへお届けする準備に入ります。
また授乳期の幼猫はミルクボランティアさんに委託して、生後二ヵ月頃に再びセンターに戻してもらい、できるだけ多くの命を、譲渡へと繋ぎます。

▲新たな家族を待つ鬼太郎くん

「群馬県動物愛護センター」の守りたい小さな命
群馬県動物愛護センターが、猫のために最も力を入れている活動が「飼い主のいない猫対策支援事業」、通称「地域猫活動」です。
群馬県では自治会等の許可を得た地域団体の地域猫活動に積極的に協力、支援。
猫を保護するための捕獲器の貸し出しはもちろん不妊去勢手術(TNR)の手術費用も助成しています。
「不妊・去勢手術に関しては、地域のボランティア団体が、捕獲器で保護したのち、県が提携している動物病院に直接出向いて手術をしてもらいます。その費用は県から獣医師会にお支払いしているので地域団体とは直接現金のやり取りはしません。現在では22地域団体が地域猫活動に取り組んでいますが、大きなトラブルもなく、貸し出し用にある捕獲器40数台も常にフル稼働という状態です」とセンター係長の山本久美子さん。

▲清潔に保たれた猫舎
不妊去勢手術(TNR)の手術費の助成金は一部という自治体が多い中、群馬県の助成金は全額支給。その費用はふるさと納税(※7)で、寄付を募っているといいます。
「地域猫活動」は、その地域で暮らしているいわば「野良猫対策」。
そのため、猫が好きな人だけの問題では済まず、地域全体で理解を求めていくことが不可欠で、センターでは地域猫活動のメリット、地域猫活動に至るまでの手順を詳しく書いた冊子(※8)を作成し、地域猫活動を広く推進する取り組みも行っています。
「群馬県動物愛護センター」次長さんに聞きました
当センターで、次長を務める手塚秀さん。
北関東には珍しく、野犬が少ないことは喜ばしいことですが、飼い主さんの飼育状況にはまだまだ課題があると言います。
「ご存知の通り、収容される犬のほとんどは飼い犬で、しかも迷い犬。返還率が6割ということも考えると、捨てたわけではなく、飼い方に問題があって、逃げてしまったというケースです。犬の飼い主の飼育・飼養を、重点的に指導する必要があると思います。そういった意味で、ぐんま犬猫パートナーシップ制度は、今後ますます生きてくると思います」

▲左から職員の塩田さん、山本さん、次長の手塚さん

始って間もない「ぐんま犬猫パートナーシップ制度」。
現在も登録してくれる動物取扱事業所を募っていることから、今後、事業者さんによる、きめ細かなアドバイスや指導が地域レベルで広がり、適正飼養・飼育が確実に根付いていくことでしょう。
群馬県動物愛護センター
住所:〒370-1103 群馬県佐波郡玉村町桶越305-7
電話:0270-75-1718
開館時間:平日 午前8時30分~午後5時15分まで
URL :群馬県動物愛護センター

取材・記事:今西 乃子(いまにし のりこ)
児童文学作家・特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会理事
主に児童書のノンフィクションを手掛ける傍ら、小・中学校で保護犬を題材とした「命の授業」を展開。
その数230カ所を超える。
主な著書に子どもたちに人気の「捨て犬・未来シリーズ」(岩崎書店)「犬たちをおくる日」(金の星社)など他多数。